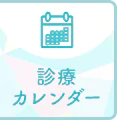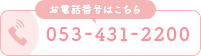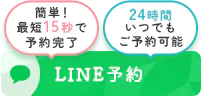「軽度異常」と「要再検査」
企業健診や地域の胃がん検診で胃バリウム検査を受けた際、「軽度異常」や「要再検査」と通知されることがあります。この結果を受けて、二次検査として胃カメラをご検討される方もいらっしゃると思います。実際の検診結果を見ると、B判定(胃ポリープ)やC判定(胃炎)とコメントされているケースが多いです。実はこれら判定区分の意味は「胃カメラによる精密検査は不要、来年も健康診断をお受け下さい」です、どうぞご安心下さい。
保険診療の胃カメラが必要なのは、D判定(要精密検査)と明記されている場合のみです。
胃バリウム検査で異常のあった方が
疑われる病気
胃バリウム検査は、胃の粘膜にバリウムを付着させ、レントゲン撮ることで胃の状態を調べることができる検査です。バリウム検査を行うことで以下のような点から、どのような疾患が隠れているかを推測しています。
造影剤のはじき像(透亮像)
レントゲン撮影時にバリウムが抜けて見える様子を透亨像と言います。透亮像が観察された場合、その部分にポリープがある可能性が考えられます。 疑われる疾患・・・胃がん、胃ポリープ、胃悪性リンパ腫、胃粘膜下腫瘍など
バリウムの溜まり像
(ニッシェ、バリウム斑)
レントゲン撮影時に一部にバリウムが濃く溜まって見える様子をニッシェと言います。ニッシェは粘膜の表面に陥凹部分(へこんでいる部分)ができており、その部分に潰瘍やがんがある可能性が考えられます。 疑われる疾患・・・胃潰瘍、陥凹性胃がんなど
粘膜不整像(アレアの不整)
胃の粘膜には、アレアと呼ばれる一定の模様があります。胃炎などの異常が起こっている場合、この模様(アレア)が不規則になることがあります。不規則な状態を粘膜不整像と言われます。 疑われる疾患・・・胃炎(ピロリ菌感染)、胃がんなど
変形像
変形像とは、潰瘍などが原因となり胃・十二指腸に変形が見られる状態を指します。潰瘍やがんが原因であることもあるので注意が必要です。 疑われる疾患・・・胃潰瘍、進行胃がん、十二指腸潰瘍など
硬化像
硬化像とは、レントゲン撮影時に胃の膨らみが悪く、粘膜がゴツゴツしたような状態が見られた場合を指します。 疑われる疾患・・・進行がん、スキルス胃がんなど
胃バリウム検査と胃カメラの違い
※この表は横にスクロールできます。
| 胃バリウム検査 | 胃カメラ | |
| メリット | ・検査費用が胃カメラに比べ安い ・胃の全体像を把握できる ・スキルス胃がんの発見率が高い ・動きをリアルタイムで確認できる |
・状態が良ければ検査間隔をあけることができる (2年毎とか3〜5年毎など) ・気になった部位の生検が可能 ・直接観察し、小さな病変も発見できる ・被ばくの心配がない ・検査後の下剤が不要 |
| デメリット | ・初期のがんは検出しづらい ・原則毎年検査しなくてはならない(検査精度が低い) ・X線による被ばくがある ・異常が見つかった際は、内視鏡検査が必要になる ・検査後に下剤服用が必要 ・胃液が多いと検査精度が下がる |
・咽頭反射がおこる可能性がある |
胃バリウム検査と胃カメラはそれぞれにメリット・デメリットがあります。胃カメラは、直接胃の中を観察できるため、診断の正確さは胃バリウム検査よりも優れています。ピロリ除菌後など胃がんリスクのある方におすすめです。なお、保険診療で行う胃カメラは適切な医学的理由と、適切な検査間隔の2つが必要です。2つの要件を満たさない場合は自費検査となります
ピロリ菌に感染していない健康な方が胃がんを発症することは非常にまれであり、胃がんの99%はピロリ菌感染中(または除菌後)の患者様に生じます。かつてはピロリ菌感染率が高く、また胃がん発症との関係性も不明点が多かっため、多くの人が毎年胃カメラを受けていました。しかし、今ではピロリ未感染の健康な方が胃がんを心配して毎年自費で胃カメラを行うことは推奨されていません。
当院は、医学的に胃カメラを必要とする患者様へ きちんと検査機会をお届けできるよう 診療体制を整えております。そのため、「毎年やっておきたいから」「お勤め先から毎年と義務づけられて」といった健康チェック目的での定期胃カメラは、いまのところは承ることができません。
どうか ご理解とご協力をいただけますよう、何卒よろしくお願い申し上げます。
胃カメラ実施の流れ
当日の朝
前日の21時までに夕食を済ませ、朝食を摂らずにご来院ください。 朝に服用している薬がある方は、事前に医師にご相談ください。
ご来院
ご予約いただいたお時間にご来院ください。 お時間になり次第、鎮静剤の投与などの検査準備を開始いたします。
検査
検査準備が終わり次第、胃カメラを実施いたします。 鎮静剤の作用でウトウトした状態で、少ない苦痛で検査を受けていただくことができます。
検査結果説明
検査が終了し、リカバリールームでお休みいただいてから、実際の検査の画像をお見せしながら結果の説明をさせていただきます。 説明の際に、気になることがございましたら、お気軽にお申し付けください。 医師がお答えいたします。